COMMENTS
世にも不幸な星の下に生まれた男、韓国人のユン・チャンス。ユン・チャンスのすべてにケチのついた地獄廻りのような人生も、彼の人生で一番初めに手放した夢である“馬”に辿り着くまでの些細な出来事だったかもしれない。
犬童一心監督が、この「やまぶき」という映画をご覧になって、是非わたしにと薦めて下さったのだそうだ。
タイトルバックの暗転が明けた瞬間だけで、犬童さんが「是非に」と仰った意味が、一瞬でわかったような気がしました。
この、奥の方からこころが震える感覚って、いったいなんなのでしょう。
画面の中の密度みたいなものに圧倒されていました。その真摯な想いはエンドロールに至るまで、しんしんと伝わってくるようでした。
言葉にならないとはまさにこのことで。強く思うのに、語ろうと思う言葉は、どれも陳腐に思えてしまってくだらない。
そんなもんだから、考えるほどに自分が剥き出しにされてしまったような良い気持ちになってきて、ただただ「映画って本当にいいもんですね」って言葉を大声で言いたくなりました。
とにかく、ほんとうに素晴らしかった。
トマトの収穫期で忙しく、試写に立ち会えないとアナウンスがあった。嬉しくなった。
監督がいない理由史上ベストワン。
『やまぶき』は、「勇気」を持って世界に向かって手を差し出す。握り返すと受粉して、世界中の街角に『やまぶき』は咲いていくんだな、と、17歳みたいな気持ちになれた。
スクリーンに「いつか」「きっと」二つの言葉が、雲のように浮かんでは、消える。
人生の不安定な斜面、揺れてしまうことを楽しむユーモア、それが生きのびるコツだと言っていた。同意します。山﨑監督の次回作でもっと笑いたいな。
岡山の地方都市。
そこに生きる人々、彼らが抱くささやかな夢。それが交差し、厳しい現実に直面すると同時に、新たな関係が生まれ、明日に踏み出す。
山際に、あえかな花を咲かす山吹のように、名もない人、ひとりひとりの命が輝く瞬間を、山﨑樹一郎は、見事に浮かび上がらせた。
あの少女、やまぶきという名前だなんて、素敵ですね。刑事やってる親父がつけたんですかね。だけどこの映画で説明されるやまぶきという花は、日陰に咲きがちだの、賄賂だの。なんでだよ。やまぶきは、素敵です。
チャンスという名前も素敵です。不幸に見舞われっぱなしのチャンスさんに、少し、笑ってしまいます。
見過ごされがちな人や物を交差させながら、16ミリフィルムの上にぐいっと乗せて差し出された政治的な映画ですが、チンピラ、ドンパチも出てくるし、ボーイミーツガールなんかも出てくる。それらが「ぎゅっ」と正しくおさめられたショットの連続。すると素敵な映画になりましたとさ!という魔法を感じました。山吹色に似て鮮やか。
坂道を転がる小石が次第に大きな落石ともなるように、ひとびとの間を行き交う小さな思惑や行き違い、恋、裏切りが少しずつ違った誰かを突き動かし、違った何かを生み出していく群像劇。山﨑樹一郎は、カメラとカメラの小さな動きだけで、その全てのあらましをおだやかにまるごと描き出すことができる希有な才能を持つ作家である。人々が行き交う交差点には、小さな花がひっそりと咲いている。その花の名は、やまぶきと呼ばれる。
『やまぶき』は人間の尊厳について、声にならない声で抗い、生き続けることについて、教えてくれる。「なんか叫びたいことないの?」という問いは静かに投げられるが、波紋は大きく広がっていく。山﨑樹一郎さんは映画という営みを信じている。闇の中で映画という営みを観る人間を信じている。
山﨑樹一郎の映画的感受性は、仰角と俯瞰、物理的な高低差を権力関係に直接に結びつけるような鈍いものではない。 (劇場用パンフレット寄稿文より抜粋)
人が他者に対して善い行いをするのは、自分自身への罪滅ぼしなのかもしれない。
それぞれ異なる場所で起きた、始まりはほんの小さな出来事たちが、出会い、大きな塊となって「困難」として登場人物たちに迫ってくる。本来出会うはずのなかった二人の人間が、道端で出会ってしまう。「ふたり」も「困難」となってしまった出来事たちも、出会いは偶然ではなく必然だったのだろう。なぜならこれは「フィクション」であり作られた物語なのだから。それなのになぜこんなにも胸に迫ってくるのか。まだ会ったことのない監督・山﨑樹一郎さんの誠実さ切実さと真摯さに、襟を正される思いがした。
『やまぶき』は、わたしたちが路傍の石もしくは花に過ぎないということ、そして予測できない自然の中に因果応報を生きざるを得ないということを山﨑樹一郎の優しさでみつめている。
これは何とも不思議だった。どこかの地方都市の些細な出来事を見ているうちに、突然視界が遠くまで開ける。人々が行動を開始する。時間さえ自由に漂い始める。作者が不思議なのか、映画というものがそもそも不思議なのか。たぶん両方だ。
どれだけ悲惨でも、奇跡でも、別に劇的じゃない。こんな目に遭ったのに、誰も見ていなくて、惨めさに泣けたり笑えたりする。この映画は、人々に覆いかぶさる理不尽さや矛盾に、地方に見る日本という国を透かしながらも、それさえも素朴なままに描こうとしていると思えるのです。(劇場用パンフレット寄稿文より抜粋)
ローカルエリアの過疎化、外国人労働、保証保健制度、厳しい題材を何処か穏やかな眼差しで包み込んで我々の日常に繋げてくれるサイレントスタンディングの様な作品
映画を観ながら、だからニッポンはダメなんだ、ついでに、オレもダメなんだと、想い続けた。それゆえ、ラストショットにどれだけ救われたことか。
複合的でありながら、監督の意図はひとつ。日陰にあるものに、あえて光をそそぐのが、映画。どんなジャンルの映画であろうと、ひとびとの自尊心をえがくのが、映画。さまざまな科白が、心に刺さったが、カン・ユンス氏始め俳優陣のなにも語らないショットが、最も印象に残った。そして、物事の善悪を単純化させないところに、監督の覚悟を感じ、感銘を受けた。これは、アジアとニッポンの映画だ。
映画で描かれる諸問題は、ビリヤードの玉のようにキューに弾かれてチリヂリバラバラなって広がっていく。
どの玉1つとして穴に落ちようとはせず、見事に卓上に広がる色とりどりの玉は夜空の満天の星のように美しい。
16ミリフィルムで撮られたこのヘンテコな映画はやまぶきの視点で、諸問題が少しずつ動いていく様をそっとみている。
『やまぶき』は、どこかにありそうな現実を信じさせようとする単なるフィクションではない。映画を作るという行為によって、この地上と、そこから遠く隔たった外側の世界との埋められない距離を測定し、歩み出す道を見出そうとする勇敢な思考の現実なのだ。
映画後半に至らんとするあるシーン、「変わりたい」「変えたい」というようなやり取りを見ていたら思わず顔がクシャクシャになってしまっていた。その後の展開は、感動とか胸に迫ったとかでは片づけられない。こんな体験は初めてだった。岡山県の真庭から日本へ、世界へ、またも放り投げられた石ツブテ。山﨑樹一郎の映画を見続けて来て本当に良かった。
何気ない日常を淡々と描く映画なのかと思いきや、奇想天外な展開に驚いた。でもギリギリのところで滅茶苦茶にはならない。決壊せずに踏みとどまるのは、作り手が土に根を張った生活をしているからであろう。不思議な手触りの映画である。
「大きい」ものが、ぼくたちを滅ぼしにやって来る。だから、「やまぶき」は、滅ぼされようとするあらゆる「小さな」もののために、彼女の回りにある「小さな」ものたちのために、「顔」をこちらに向けるのである。そのときには、もうプラカードも不要だ。なぜなら、「顔」は、「汝、人を殺すなかれ」と書かれたことばだからである。(劇場用パンフレット寄稿文より抜粋)
いつしか流浪者になってしまった者。自分の行く先がまだ何も見えていない者。意図せずこの場所に縛り付けられた者。
固有の物語を背負った人々がてんでばらばらに奔走し、ロードムービー、家族映画、チンピラ映画、青春映画、いくつもの小さな映画をそれぞれに展開する。
そしてこの無数の映画群は、一瞬交わり、またもばらばらに解けていく。
こんなユニークな映画は初めてだ。
人はこんなにもポロポロと乾き、崩れ落ち、それでもなお、静かに歩みだす。
16mm撮影(とスパイスのようなアニメーション)が映し出す、人間のあり方についてのザラザラとした寓話。
長年写真フィルムの開発者であった父は、「フィルムは粒子の世界で、デジタルは線の世界」と言っては、今は稀になってしまったフィルムの映像を見るたびに荒い粒子の柔らかさに目を細める。
『やまぶき』も、岩山が砕かれるオープニングシーンから、16mmフィルムの粒子の世界に観るものを魅了する。描かれるのは、さまざまな距離感を保ちながら隣り合わせに生きる人々の群像劇。粒子のように彷徨いながら化学反応を起こし、運命が連鎖し、交差していく。分断の世界で生きる私たちに、フィルムで描かれる物語は、予期せぬ流れに抗えず、立ち止まりながらも動かされ、すれ違いながらも揺すぶられる私たち一人一人の繋がりの動きを見せてくれる。砕けた山は土になり、そこに芽吹くのは、分断を生む線引きの世界ではなく、それぞれの視点から未来を見つめるように優しく促してくれる『やまぶき』そのものであると感じた。
種をまくと、芽吹きの遅いもの、強いのに負けてしまう芽が必ず出てくる。真っ直ぐ伸びられない芽もある。「そういう芽にこそ、もっと光を」そんな思いを受け取ったような気持ちになった。
タイトルを役名とする祷キララの立ち姿、その花のような可憐かつ無骨な存在感がひときわ胸に迫った。どうにも解きほぐせない現実を前にして、できることは極めて少ない。行動や言葉の実効性には大きな疑問符がつく。その極めてわずかな、現実を変えるには明らかに不足な何かを、人はそれでも尚すべきだろうか。答えはない。が、『やまぶき』は問いそのものを生きる。しんどい映画だ。それを見た者は当然、解決しがたい問いを植え付けられる。でも、その問いだけが安易な答えから人を守るだろう。今だからこそ、この映画が存在することの意義は限りなく大きい。問いを抱え続ける山﨑樹一郎の歩みは力強く、本人にそんな気はなくても同じ時代に生きる者を勇気づけている。
映画は声なき声を可視化する。表現の果たせる大いなる役割を当たり前のような静けさでやってのけてくれた作品でした。
祷キララさんの透徹な視線がとても好きでした。
そういえば山吹の花言葉は「気品」だった。この作品にとても相応しい言葉だと思う。監督は否定するかもだけど。
映画の隅々に、無駄を削ぎ落とした画面の経済性とはっと胸を打つ光の美しさが同居している。僕たちに、この光を決して見逃してはならないと語りかける画面の緊張こそが、引きつけて離さない映画の力となる。
一人一人の命のカケラたち。
両手でかき集めても、指の間からこぼれ落ちてしまう。
決して甘くない人生なのだけど、
なんでだろう、
彼らの涙は優しくってとても温かい。
山﨑さんの映画はデビュー作『ひかりのおと』からずっと観続けているが、彼ほど映画に純愛を捧げている人を僕は知らない。陽の当たらない場所で作り続けた魂は『やまぶき』でたしかに芽吹いた。彼の一番の仕事だ。同じ時代を走ってきた朋輩として嬉しく、その純粋さに背筋が伸びる思いだ。
岡山の採石場と街頭から発せられる、グローバルな物語。個人レベルから国際政治レベルまで、実に多彩な主題をまとめあげる山﨑監督の語りの上手さが際立っている。山吹という花の可憐な姿は、現代のさまよえる魂たちの平穏を希求するかのようだ。日本のインディペンデント映画の土壌の豊かさを証明する作品であり、本年必見の1本。
16ミリフィルムの粗く冷たい粒子が描く心のざらつきを、拭い去るかのごとく、誠実なストーリーテリングと祷キララの真直すぎる目線が眩しい。生活の中で感じる矛盾や問題意識が少しでもクリアになる可能性を見せてくれる。
美しく、儚く、言葉に頼らずに、多くを伝えてくれる。類を見ない方法で隣人たちと生きる方法を探求する作品。政治的主題を、声高にではなく、非常に繊細に捉えている。私にとって『やまぶき』は恩寵だ。
主人公たちの心の揺らぎが16ミリフィルムのざらついた映像に見事に表現されている。編集も秀逸で、とりわけシーンの移行が素晴らしい。落ち着いたカメラの動きが私たちを物語へ自然と誘う。だが、それらの技術的な要素以上に『やまぶき』が真に優れているのは、人生のあらゆる困難にポジティヴに向き合う道を示していることだ。
日の当たらぬ場所に咲く山吹のように不可視な人々の物語を、優しさとともに、明らかに政治的な視点から描く作品だ。幸せを得るには岩場に芽吹くしか手段がない、日陰に生きる人々の物語だ。
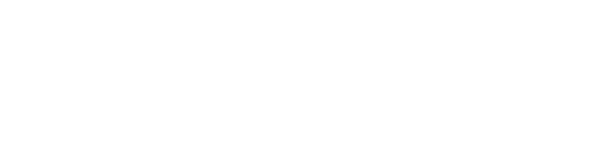










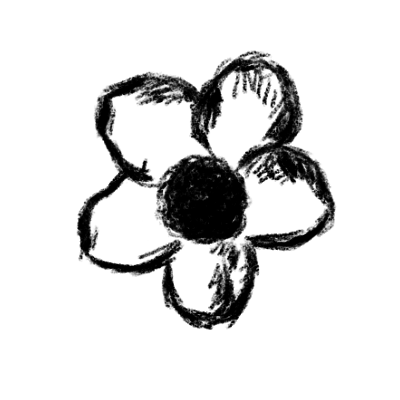
COMMENTS
タイトルバックの暗転が明けた瞬間だけで、犬童さんが「是非に」と仰った意味が、一瞬でわかったような気がしました。
この、奥の方からこころが震える感覚って、いったいなんなのでしょう。
画面の中の密度みたいなものに圧倒されていました。その真摯な想いはエンドロールに至るまで、しんしんと伝わってくるようでした。
言葉にならないとはまさにこのことで。強く思うのに、語ろうと思う言葉は、どれも陳腐に思えてしまってくだらない。
そんなもんだから、考えるほどに自分が剥き出しにされてしまったような良い気持ちになってきて、ただただ「映画って本当にいいもんですね」って言葉を大声で言いたくなりました。
とにかく、ほんとうに素晴らしかった。
監督がいない理由史上ベストワン。
『やまぶき』は、「勇気」を持って世界に向かって手を差し出す。握り返すと受粉して、世界中の街角に『やまぶき』は咲いていくんだな、と、17歳みたいな気持ちになれた。
スクリーンに「いつか」「きっと」二つの言葉が、雲のように浮かんでは、消える。
人生の不安定な斜面、揺れてしまうことを楽しむユーモア、それが生きのびるコツだと言っていた。同意します。山﨑監督の次回作でもっと笑いたいな。
そこに生きる人々、彼らが抱くささやかな夢。それが交差し、厳しい現実に直面すると同時に、新たな関係が生まれ、明日に踏み出す。
山際に、あえかな花を咲かす山吹のように、名もない人、ひとりひとりの命が輝く瞬間を、山﨑樹一郎は、見事に浮かび上がらせた。
チャンスという名前も素敵です。不幸に見舞われっぱなしのチャンスさんに、少し、笑ってしまいます。
見過ごされがちな人や物を交差させながら、16ミリフィルムの上にぐいっと乗せて差し出された政治的な映画ですが、チンピラ、ドンパチも出てくるし、ボーイミーツガールなんかも出てくる。それらが「ぎゅっ」と正しくおさめられたショットの連続。すると素敵な映画になりましたとさ!という魔法を感じました。山吹色に似て鮮やか。
それぞれ異なる場所で起きた、始まりはほんの小さな出来事たちが、出会い、大きな塊となって「困難」として登場人物たちに迫ってくる。本来出会うはずのなかった二人の人間が、道端で出会ってしまう。「ふたり」も「困難」となってしまった出来事たちも、出会いは偶然ではなく必然だったのだろう。なぜならこれは「フィクション」であり作られた物語なのだから。それなのになぜこんなにも胸に迫ってくるのか。まだ会ったことのない監督・山﨑樹一郎さんの誠実さ切実さと真摯さに、襟を正される思いがした。
複合的でありながら、監督の意図はひとつ。日陰にあるものに、あえて光をそそぐのが、映画。どんなジャンルの映画であろうと、ひとびとの自尊心をえがくのが、映画。さまざまな科白が、心に刺さったが、カン・ユンス氏始め俳優陣のなにも語らないショットが、最も印象に残った。そして、物事の善悪を単純化させないところに、監督の覚悟を感じ、感銘を受けた。これは、アジアとニッポンの映画だ。
どの玉1つとして穴に落ちようとはせず、見事に卓上に広がる色とりどりの玉は夜空の満天の星のように美しい。
16ミリフィルムで撮られたこのヘンテコな映画はやまぶきの視点で、諸問題が少しずつ動いていく様をそっとみている。
固有の物語を背負った人々がてんでばらばらに奔走し、ロードムービー、家族映画、チンピラ映画、青春映画、いくつもの小さな映画をそれぞれに展開する。
そしてこの無数の映画群は、一瞬交わり、またもばらばらに解けていく。
こんなユニークな映画は初めてだ。
16mm撮影(とスパイスのようなアニメーション)が映し出す、人間のあり方についてのザラザラとした寓話。
『やまぶき』も、岩山が砕かれるオープニングシーンから、16mmフィルムの粒子の世界に観るものを魅了する。描かれるのは、さまざまな距離感を保ちながら隣り合わせに生きる人々の群像劇。粒子のように彷徨いながら化学反応を起こし、運命が連鎖し、交差していく。分断の世界で生きる私たちに、フィルムで描かれる物語は、予期せぬ流れに抗えず、立ち止まりながらも動かされ、すれ違いながらも揺すぶられる私たち一人一人の繋がりの動きを見せてくれる。砕けた山は土になり、そこに芽吹くのは、分断を生む線引きの世界ではなく、それぞれの視点から未来を見つめるように優しく促してくれる『やまぶき』そのものであると感じた。
祷キララさんの透徹な視線がとても好きでした。
そういえば山吹の花言葉は「気品」だった。この作品にとても相応しい言葉だと思う。監督は否定するかもだけど。
両手でかき集めても、指の間からこぼれ落ちてしまう。
決して甘くない人生なのだけど、
なんでだろう、
彼らの涙は優しくってとても温かい。